|
|
 |
|
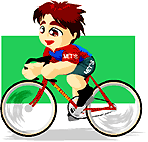 運動療法を行う目的には、以下のものがあります。 運動療法を行う目的には、以下のものがあります。
- 肥満を改善する
- インスリンの感受性を高める
- 乏しいインスリンを節約する
- 筋肉を増強する
- 心肺機能を高める
- ストレスを解消する
運動のポイントとしては
- .メディカルチェックを受けてから始める
主治医から必ずメディカルチェックを受け、運動をしてもいいかどうかを調べます。
運動量や方法によっては、かえって症状を悪化させてしまう場合があるので注意が必要です。
- .無理なくどこでもできる運動をする
ウオーキングや自転車、室内の自転車こぎなどがよいでしょう。短時間でできる全身運動としては
水泳が理想です。楽しく継続できる運動がいいですね。
- .一定時間、持続する運動をする
運動を始めて10分位経過すると、血糖値が下がり始めます。運動は食後1〜2時間後に少なくとも
20〜30分は続けることが大切です。
また、空腹時に運動をすると薬物療法を行っている人は低血糖に陥ることがあるので避けましょう!
- .運動量は適度に(やりすぎると害になることがあります)
目安としては1日7000〜10,000歩が目標です。運動の強さは心拍数を目安に自分にあった強度を見つけます。
の4つがあげられます。ただし、運動療法を行ってはいけない場合もありますので、医師の指導に従いましょう。日々の生活に楽しく無理なくできる有酸素運動を上手に取り入れると良いでしょう。
|
|
- 運動療法の効果
1)筋肉中の糖が使われる。同時にインスリンの働きも良くなるので血糖は低下する。
2)血中の総コレステロールや中性脂肪が低下する
3)血液の循環がよくなり、心臓や肺の機能が増強される。
4)末梢神経への血流もよくなり、末梢神経の障害の改善に役立つ。
5)頭脳に活力を与え、気分を爽快にして、ストレス解消に役立つ。
- 安全に運動を行うために
1)運動前の準備運動と、運動後の整理運動は忘れずに行う。
2)他人とおしゃべりしながらやれる程度の強さの運動を15〜20分以上続け、運動昼夜終わったあとに体の苦しみや痛みがなく、翌朝にも疲労や運動の後遺症が残らない程度の運動がよい。
3)寒いときは保温に努め、厚いときや汗をかいたときには、水分補給も忘れずに行う。
4)その運動に適した服装や靴を用意し、体調が悪くなったら途中で休む
- 運動を長続きさせるために
1)生活習慣の一部となり、毎日実行できる運動(通勤の往復など)
2)相手を必要とせず、経費のかからない運動(歩行など)
3)前身の筋肉を動かす運動(体操や歩行など)
一番安全な運動で簡単な運動は歩行である
- 歩行は運動の基本
1)特別の用具を必要としない、誰でもできる運動。代表的な全身運動。
2)まずは一日5,000〜6,000歩を努力目標にする。
- 運動は一定時間持続すること
1)運動を葉J馬手10分を過ぎる頃から、血中ブドウ糖の筋肉への取り込みが目立って増加し、そのために血糖は下がります。そのため、一定以上の強さの運動を20〜30分間は持続することが大切。
2)運動が長くなると、逆に低血糖や疲労も起こるので、長ければ長いほど良いわけではない。
- 毎日継続して行うこと
- 一日の運動量は?
一日160キロカロリー(食品交換表の2単位に相当)の運動を行うと1週間で1120キロカロリーとなる。
- 適度な運動の強さ
1)40〜60%の強さが適切
2)今まで運動をしていなかった人や高齢者は30〜40%の強さから始めるとよい
- 食事との関係
1)できれば血糖の高くなる食後30分から2時間の間に行うとよい
2)この時間帯に無理な人は、確実にやれる時間を選んで行う
3)空腹時の運動は低血糖の心配があるので、食膳に行う場合は、1〜2単位の軽食を運動前に取る
4)普段に比べて運動量が多いときは、増えた分だけ食事量も多く取る
|
|



